庭園日誌をご覧のみなさま、こんにちは。
スタッフの【川瀬】です。
突然ですが、"植物"とはなんですか?
この問いかけ、難しいですよね。
皆さんなら、どう答えますか?
「葉っぱや茎、根を持つ生物」、
「動物の対になるグループ」、
あるいは、「太陽の光から栄養を得る(光合成をする)生物」・・・
色々思い浮かびますが、
「これだ!」という定義ができる方は多くないのではないでしょうか。
実は学問の世界でも区分のしかたが幾通りかあって、
植物の定義は一つに定まっているわけではありません。
ここでは、辞典に載っている定義をご紹介しておきましょう。
しょく- ぶつ【植物】
生物界を二大別にした場合,動物に対する一群。草木・藻類などの総称。
細胞壁があり,クロロフィルなどの光合成色素をもち,
独立栄養を営む,などの特徴を有するが,
細菌類・菌類・種子植物の一部では腐生または寄生するものもある。
(三省堂・大辞林より)
さて、今回はそんな植物の分類に関するお話です!
木と草
では、ここでもう一つ問題です。
"木"(木本植物)と"草"(草本植物)の違いはなんでしょう?
「木は大きくて草は小さい」という答えは、
残念ながら不正解に近いです。
人の背丈より大きくなる草もあれば、
成木でも小さいままの木だってありますよね。
では、正解はというと?
当記事では、ふたつの要素に分けてその違いをご説明します!
寿命
何十年も生え続ける草、あるいは一年ごとに枯れてしまう木
なんて聞いたことがありませんよね。
そう、木と草の大きな違いの一つが寿命です。
木は数十年から数百年、時には数千年に渡って生き続けることもあります。

鹿児島県の屋久島。古木として有名な縄文杉の樹齢は3000年を超えると言われる。
一方、多くの草は一年で世代を交代したり、生え替わったりします。
多年草の中には、数十年に渡り生育するものもありますが、
木に比べれば短いものです。

リュウゼツラン(草本)の寿命は数十年。大きく育った茎はテキーラ酒の原料となる。
では、どうしてこのような違いが生まれるのでしょうか?
その理由は、植物の身体の構造にあります。
構造
樹木の構造を考えるうえで欠かせないもの、それは「形成層」です。
草は形成層を持っていないか、持っていてもあまり発達していません。
形成層は樹木の樹皮の内側にある組織で、
細胞分裂を繰り返すことで樹木の幹を太くする(=肥大成長させる)役割を担います。
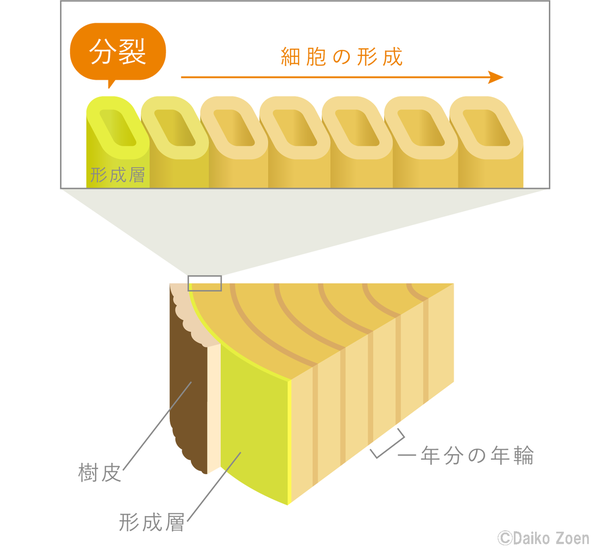
形成層があるからこそ、木は年を重ねるごとに大きくなることができるのです。
また、木と草の細胞を見比べてみると、
ここにも大きな違いがあることが分かります。
簡単に言ってしまえば、「堅いか、堅くないか」です。
樹木の細胞は、リグニンという物質が入り込むことによって
頑丈になることが知られており、これを「木化(木質化)」と言います。
樹木の巨体を支えるためには、木化によって
ひとつひとつの細胞の強度を増す必要があるのです。
以上ふたつの理由から、
「木の幹は太くて堅い」&「草の茎は細くて柔らかい」
という形態の違いが表れているというわけです。
木が毎年成長することができ、
その大きく成長した体を支えられる理由が分かりましたね。
まとめ
Check!
木は、草よりも寿命が長い。
木が長生きできるのは、形成層や細胞の木化のおかげ!
木と草の違い、お分かり頂けたでしょうか。
今回ご説明したのはあくまで一般的な事柄ですので、
中には例外も存在します。
例えば、竹。

竹は多年生ですが、形成層を持たず肥大成長を行いません。
一方、細胞は木化するので、頑丈な茎を持っています。
竹は草の仲間に入れられることも多いのですが、
厳密には木とも草とも分けられない存在なのです。
このように一筋縄ではいかないのが、
分類の面白いところかもしれませんね。
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました!
↓お庭のお手入れ・改修・設計などに関するご相談はこちらから!↓
-------------------------------------------
株式会社大幸造園
TEL 075-701-5631
FAX 075-723-5717
HP http://daiko-zoen.com/
-------------------------------------------
